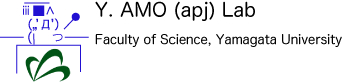低振動数ラマン散乱
研究の現状について
通常のラマン散乱では300 cm-1以上の振動数領域を測定する。この振動数領域は、波長でいうと赤外線の領域で、分子の基準振動や格子振動に起因する散乱が現れる。
およそ300 cm-1以下のラマン散乱を、低振動数ラマン散乱という。低振動数領域では、液体であれば分子間の振動や衝突に起因する散乱散乱が、結晶であれば格子振動の一部といわゆるセントラルモードが、不規則構造系であればボゾンピークに対応する散乱が観測される。
分子間の振動や衝突の情報を得られることから、当初は、液体の動的構造の研究のためにラマン散乱を用いることにし、様々な液体の低振動数ラマン散乱の組成・温度依存性を測定してきた。
一方、赤外とラマンは相補な測定方法として知られている。分子や結晶の振動モードは、振動の対称性によって、ラマンと赤外の両方、いずれか一方に活性、あるいは両方に不活性となる。ラマンと赤外の両方に活性な振動モードの振動数は(原則として)等しい。赤外とラマンを両方測定することで、最も多く分子振動の情報を得られることから、赤外とラマンは相補であるとされてきた。
赤外領域よりずっと低いマイクロ波領域での電磁波の吸収プロファイルは、複素誘電率の虚部、即ち誘電損から求めることができる。誘電損に角振動数ωを掛けたものが吸収係数となり、マイクロ波からミリ波、サブミリ波、遠赤外領域へと延びてゆき、赤外吸収のスペクトルへとつながっていく。昔は、サブミリ波〜遠赤外領域の測定が難しかったので測定がほとんど行われていなかったが、THz-TDSの普及により、スペクトルの穴が埋まってきている。
ラマン散乱も、分光器の進歩や、干渉分光を組み合わせるといった工夫により、マイクロ波領域までのラマン感受率を測定できるようになった。
水やアルコールなど分子間に水素結合が存在する液体は、マイクロ波領域に誘電緩和があらわれるので、積極的に誘電緩和の測定が行われてきた。スペクトルの濃度変化や温度変化を液体の動的構造と結びつけて解釈されることが多い。赤外とラマンは相補な情報を与えるのだから、誘電損と低振動数ラマン散乱の感受率も相補なはずであり、誘電緩和と重なる領域まで低振動数ラマン散乱を測定すれば、緩和モードの分子運動の起源についてさらに詳しい情報が得られるのではないかと考えた。そこで、まずはエチレングリコールや水について、マイクロ波領域までラマン散乱を測定したところ、感受率のピークは全く一致しなかった。つまり、赤外ラマンの相補性はマイクロ波領域では(多分THz以下、数cm-1以下あたりのようだがどこで破れるかを測定で直接決めるのは難しい)破れているということがわかった。
相補性が成り立たないので、相補性を利用して誘電緩和と低振動数ラマン散乱をつき合わせて液体の研究をするというアイデアは当面は進められないことがわかった。まずは、なぜ相補性が成り立たなくなるかをはっきりさせないと、液体の研究にどう利用できるかもわからない。
Bern&Pecoraは、古典電磁気学と熱力学に基づいて、吸収と散乱で緩和時間が3倍違うことを示したが、導出の前提となったモデルが水素結合のある液体のような複雑な系にそのまま適用できるとは考えがたい。誘電スペクトルから主緩和を差し引いた残りが光散乱と対応するという主張もあるが、なぜ誘電の主緩和に対応するモードのみが光散乱に現れないのかということが説明できない(選択則を考えようにも対称性はすっかり落ちている)。誘電緩和とラマン散乱の最低振動数モードの緩和時間が一致するという主張をしている研究グループもあるが、特定の試料での結果で、一般性には疑問がある。このように、測定対象によっても諸説あって、どのように決着するかは予想がつかない。
私は、相補性の破れは、水素結合や個別の液体の性質によってそのまま説明できるものではなさそうだという感触を持っている。ラマンと赤外の相補性が成り立つ必要十分条件が離散準位の存在であるとすると、相補性が成り立たない領域ではエネルギーが連続準位となっている状態で遷移が起きていると考えるしかない。量子回帰定理は、量子系が離散準位のあつまりになっていれば有限時間の間に元の状態に戻ることを保証しており、現実に生じている散逸による不可逆性と回帰は両立しないことから、散逸によって連続準位が出てこないと矛盾を来す(光と物質の相互作用が回帰を確認する前に終わるので不可逆に見えているだけだから連続準位にならなくてもいいという考え方ももあり得るが、回帰も含めた全系の情報を確率的に光が持ち帰ってくるなら準位の連続性は必要になる)。簡単なモデルとして、散逸を入れた減衰調和振動子を量子化しようとすると、エネルギー固有値の下限が存在しなくなったり、不確定性が破れたりしてしまう。エルミート性を破れば困難は回避できることが見つかってはいるが、まだ減衰振動の量子化の決定版は無く、改善が続けられている。直観的には、減衰振動は古典力学では時間が経つとx=0, p=0になるが、量子力学では不確定性によってx=0,p=0になることはできないので、ずっと減衰のままではいられないということが、古典的な減衰振動のラグランジアンから出発してハミルトニアンを導出し正準量子化を行った際の「不具合」に反映しているのだろう。ある程度の大きさの揺らぎによって常に駆動されていれば不確定性が事実上破られなくなって問題を回避できそうではあるが、熱揺らぎが不確定性を覆い隠すような形になってしまい、量子論としてそれで良いのかどうかはわからない。固有値が連続準位になることを示した上で遷移速度を計算するためには、何かいいモデルハミルトニアンが欲しいところだが、光との相互作用まで取り込まないといけないので場の量子論の枠組みが必要になる。低振動数ラマン散乱と誘電緩和の実験結果は、次にやることは散逸を含んだ場の量子論の理論で、固有値の構造を(数学的に)調べることだと告げている(ように私には思える)。
そんなわけで、ずっと実験をしてきたのに急に理論をやる必要が生じて、さてどこからどうやって攻略しようか思案しているうちに時間が経っている。まあこの「そう囁くのよ、私のゴーストが」状態は、後になってみれば全くの見当違いだったということになるかもしれないが、大ハズレをやらかすのもまた研究なのだからそれも仕方がないだろう。
あと、かつて私は低振動数ラマン散乱で見えている「緩和モード」の解析では、デバイ型の仲間の関数を使うのはよろしくなく、デバイ型導出で使ったoverdamped limitとnarrowing limitの近似がTHz領域で破れるのでそれを取り込んだモデルを用いるべきだと主張して液体の低振動数ラマン散乱の解析をするという学位論文を書いた。しかしなぜ近似が破れるのかは、デバイ型導出で用いる古典的なLangevin方程式からは全く説明できない。ところで、近似が破れる領域はちょうど(素励起の=準粒子の)離散準位がはっきりと存在し始める領域でもある。揺動散逸の関係から、何かこうユニバーサルに、THz付近で固有値の構造が離散と連続の間で変わるとか熱揺らぎが不確定性を完全に覆ってしまうと状況が変わるとかがあって、それが反映して、スペクトルフィッティングの立場からみると近似が破れているように見える、という方向に繋がってくれたらいいなあ、と漠然と考えている。大体こういう問題は、数学者か数理物理学者がとっくの昔に解決していて実験屋が知らなかっただけというオチがありがちなので、まずはいろいろ探しているが見つけることができていない(理解できてなくて見逃してるだけもしれないが)。量子散逸系の必要性に最近気づいたばっかりなので(遅いよ、というツッコミは勘弁してくれ私はラマンの実験屋で研究対象は液体だった)、単に私の知識不足と理解不足でこんなことを思っているだけかもしれない。このへんの問題が既に整理されていたら、ぜひ教えてください。
発表など
- 9IDMRCSで発表した要旨。(国際会議のサイトでは発表タイトルなどが検索にかからないようなので、要旨集の表紙、自分の要旨、発表した証拠としてポスタープログラムを抜粋)