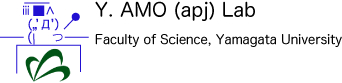ニセ科学を問題にするとはどういうことか
品質管理問題である
個別のニセ科学を、わざわざニセと指摘する行為は、世の中に出回る科学関連情報の品質管理をしていることに相当する。
供給側(=科学者)以外がニセ科学批判をするケースについては、消費者側が生活の知恵として粗悪品に注意という情報を共有する活動をしている、というのと同じになる。以下、供給サイドについて書いたけど、消費者側が自発的に同じ行動をとることもあるので、それも含めればよい。
例えば、きちんと火をつけられるマッチと、ろくに火がつかない粗悪品のマッチが両方市場に出回っていたら、まともな製品を作っている企業は、粗悪品が出回っていることに対して何らかの対策をとるだろう。最後まで使えるエンピツと、使っていると芯が折れやすくて大部分が無駄になるエンピツの両方が市場に出回っていたら、いい製品を作っている側が、消費者に対して注意喚起をしたりするだろう。
ニセ科学を問題にするというのは、いい方の製品を作っている会社が、「業界団体を作って品質向上に努め、業界として品質検査の基準を決め、検査に合格した品質保証のある製品にはこのマークやシールを貼ることにしました」とか「よく似た粗悪品に注意!ココが違います」といった宣伝をするのと同じ事をしているだけである。非専門家によるニセ科学の指摘は、消費者同士で「最近は粗悪品が出回っているけど、見分けるポイントはここですよ」といった情報を共有するのと同じ事をしているだけである。
粗悪品が出回ってて放置しておくと業界の信用が落ちそうだから何とかしましょう、という話は、科学以外では昔からあったものであり、別に珍しくも何ともない。
科学の「権威」の取り扱い
ニセ科学を問題としているときに、ニセ科学を批判している側に向かって科学の権威性を持ち出すのは全くのナンセンスであるだけでなく、不公平でもある。なぜなら、科学に権威があると思い込みあるいは権威があることを前提として、それを積極的に利用したのはニセ科学の方だからである。
科学の権威性を是として権威を騙ることも是とするならば、それはニセ科学を支持することに他ならない。
科学の権威性を否としておいて権威を騙ることを是とするのなら、それはニセ科学を支持する上に自己矛盾だろう。
科学の権威性を否としておいて権威を騙ることを否とするのなら、ニセ科学を支持する側とそれを批判する側を同時に等しく批判するのが筋であるから、ニセ科学を批判する側のみに向かって何かを主張するのは偏った態度であり、実りのある議論が成り立つことは期待できない。
残りは、科学の権威性を是としておいて権威を騙ることを否とする立場だが、これはニセ科学の定義に「科学を装う」が入っているので、ニセ科学を問題とする立場と矛盾しない。ただし、科学の権威性の程度についての認識は、最も権威があると見做した場合でも「科学は自然を近似的に記述しているだけ」という限度にとどまる。
科学の権威がむやみに使われることについて警戒する立場をとるのであれば、科学の権威を利用して他人を欺すニセ科学こそが警戒し批判すべき対象となるはずで、権威が伴っていることを理由として科学の側に注意喚起をするのはお門違いであるし、議論の立ち位置とも矛盾している。
ニセ科学と社会規範
社会規範とは何か
社会規範には、法規範、道徳規範、宗教規範、慣習規範がある(「サイエンス・オブ・ロー事始め」)。法規範は社会において強制力を伴う。「道徳規範は、個人の倫理観や道徳観が社会一般に共通するものに高められ、自然に社会規範として定着してくるもの」「宗教規範は、ある宗教上の教義が特定の信者に地してだけでなく一定の社会や地域に普及し、これが社会規範として尊重されるもの」「慣習規範は、社会のなかで長年にわたり繰り返し守られてきたことが社会的ルールとして意識され、遵守されるもの」とされている。
社会規範とは、法規範も含めた、社会生活を送る上で守った方がスムーズにいくルールで、破ると一定のペナルティ(強制力のあるものから、クレームをつけられるといった強制力のないものまで)を科されるものである。
社会規範は自然科学の法則ではなく、人と人との間で決めるものである。社会規範に違反する行為が存在するから規範が無意味だ、ということにはならない。殺人事件があるから人を殺してはいけないという社会規範を弱くしましょうとか、詐欺を行う人が現実に存在するから他人を騙す行為を少しは正当化しましょう、ということにはならない。観測事実によって法則を書き換えてきた自然科学とはルールの在り方が異なっている。
ニセ科学を問題とする場合の社会規範
ニセ科学の「ニセ」の部分を問題とする理由の1つに、「人を騙してはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」という社会規範の存在がある。もう少しくだけた言い方をするなら「嘘をついてはいけない」といったものになるだろう。
このことについて、道徳を押しつけるといった見当外れの意見が出てくるが、それは社会規範の意味を知らない、あるいは現状を把握していないことから生じている。
「人を騙してはいけない(嘘をついてはいけない)」は法規範に含まれている
「人を騙してはいけない」という内容が法規範に含まれていることは、個別の条文からわかる。いくつか実例を挙げておく。
- 刑法246条(詐欺)
「人を欺いて財物を交付させた者は」と規定されている。騙す行為すべてが詐欺行為となるわけではなく、人を錯誤に陥れて処分を導くものに限られる。不作為によるものも含まれる。 - 刑法233条
業務妨害罪の要件として「虚偽の風説を流布し」と規定されている。 - 刑法230条の2、名誉毀損については民法の不法行為責任を問う場合も同様の基準による。
名誉毀損罪の免責条件として「公共の利害に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、事実であることの証明があったときは、これを罰しない」と定めている。条件を限って、真実性・真実相当性を判断して免責する、ということであり、嘘をついていた場合には免責されることはない。 - 刑法169条、171条
法律により宣誓した場合の虚偽の陳述、虚偽の鑑定や通訳・翻訳をすると刑事罰の対象になる。 - 民法94条
「相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする」と定めている。契約成立は意思表示の合致であり、契約は守らなければならないというのが原則だが、例外として虚偽表示の場合は無効であるとした。さらに、善意の第三者には対抗できない、として無効の範囲を制限している。 - 民法96条
「詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができる」と定めた。こちらも、契約は守らなければならないという原則に変更を加えるものであるが、善意の第三者に対抗できないとすることで、変更の範囲を制限している。 - 民事訴訟法2条
「当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を通以降しなければならない」と規定している。訴訟法上の要件を具備するように故意に事実状態を作り出したり妨害したりしてはいけない、というものが含まれている。 - 不当景品類及び不当表示防止法4条
不当な表示の禁止。実際よりも優良であると消費者を誤認させる表示を禁止し、2項では、表示の「合理的な根拠」を持つことを前提とした(根拠を示せなかった場合には優良と誤認させる表示をしたとみなされる)。 - 特定商取引に関する法律6条、6条の2
不実告知の禁止。不実告知を行ったかどうか判断する際に、告知内容の「合理的な根拠」を事業者が示せなかったら、不実告知をしたとみなされる。
刑事系にも民事系にも、「嘘をついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」という規範を具体的に盛り込んだ条文があることがわかる。
裁判所で争われる場合、法が含んでいる「嘘をついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」といった規範が道徳あるいは社会慣習に合わないという理由で、法の適用が問題になったりすることは起きていない。従って、法規制の延長上にあることがらについては、法的ペナルティが科されない場合であっても守った方がよいこと、としてこれらの規範を位置づけるのは、強制でも押しつけでもない。既に我々の社会はこれらの規範を守る立場をとっていると考えるしかない。
法と道徳の関係、その他の規範との関係
現在受け入れられている考え方は、「法は道徳の一部である」というものである。これには2通りのとらえ方がある。一つは、法は社会秩序の維持のために強制しなければならない最小限度の道徳規範であり、それ以外に道徳のみで規律するものが広がっているというもの、もう一つは、法と道徳が交錯しており、交錯した部分が道徳的基盤に根ざした法(刑法など)、交錯していない部分はそれぞれ道徳のみ、法のみが問題となるとする考え方である。日本での現在の通説は後の方である。
(【補足】道徳が法を含むとしてしまった場合に生じる問題について。例えば、戦前の尊属殺重罰規定は、親孝行せよという社会道徳が背景にあった。昭和29年福岡高裁判決のケースは、親の側からの激しい暴力と性的虐待が続いた挙げ句に起きた尊属殺人事件で、社会道徳を適用すると加害者に対して非人間的な結果をもたらす。これを回避するために、道徳と法を切り離さなければならない場合がある。)
普通に考えて、法規範と道徳規範と宗教規範と慣習規範が相互に逆のことを主張し続けるというのは、原則として有り得ない。たとえば、社会規範と正面から衝突する特定宗教の教義は、社会で受け容れられることが無いばかりか、制裁の対象になる(多くのカルト宗教が引き起こした事件など)。例外としては、異なる道徳規範のどちを優先するかという問題が生じた場合に、矛盾が生じることはある。また、社会の変化に規範の変化が追いついていない場合には不合理な結果になったり、一時的に矛盾したりすることが起こりうる。
社会規範の存在を想定してよい場合
「嘘をついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」という社会規範と重なった法規範が効力を発揮するのは、社会的評価の変動を引き起こしたり(名誉毀損)、財産的被害を発生させたりする場合である。刑法の詐欺罪を構成するところまでいかなくても、不実証広告を行って消費者に物を売りつけたりしたら、行政処分の対象になる。
世の中に存在する「ニセ科学」の多くは、財産的被害を発生させる。実際、既に排除命令や行政処分の対象になったものとほとんど変わらない、あるいは相当似通ったやり方で商品宣伝をするケースが後を絶たない。商売に使われるニセ科学は、違法なものと重なっていたり、既に違法とされたものの周辺にあるといえる。であるならば、法の適用の場合と同様に「嘘をついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」という社会規範が適用されることを前提として、ニセ科学をこの社会で問題にしてもかまわない。
他に考えられる規範としては、「公共財であっても財産的被害を発生させてはいけない」「他人に危険を及ぼしてはいけない」「本人の努力で対応不可能なことを理由として社会的差別をしてはいけない」といったあたりが考えられる。このあたりまでは条文も判例もある。
これらの規範に違反することが併せて問題となっている場合に、「科学が科学以外のことまで正当化するのはけしからん」等と反論するのはナンセンスである。科学以外のこと、即ち社会規範は、科学者が決めたのでもニセ科学を問題とする人達が決めたものでもなくて、我々の社会が決めたものである。科学者を含めニセ科学を問題とする側は、単にその規範を受け入れているに過ぎない。
現実のニセ科学について検討する
上記の社会規範の存在を前提として非難に値するニセ科学とは、その内容が、実際に違法なものの周辺にあるとか、違法な行為を手助けする、あるいは他人に損害をもたらすといったものになる。そこで、これまでにニセ科学として話題になったものを列挙し、社会規範という面から検討してみる。
リストとして、少し古いが、「妄想科學日報」の「覚えておきたい、ニセ科学リスト」(2007/11/28)を参考にさせていただくことにする。陰謀系と精神世界系は、ニセ科学というよりも、非合理として問題にすべき部分が多いので省いた。
被害発生の態様として、「財産被害型・不当表示型」、「権利侵害型」、「公益侵害型」に分けてみることにする。「財産被害型・不当表示型」は、法規制の対象となっているものに最も近い。「公益侵害型」は、特定個人ではなく社会に広く損害をもたらすもの、「権利侵害型」は差別と直接結びついているものであり、「嘘をついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」とは異なる社会規範に抵触する。
- ホメオパシー:「財産被害型・不当表示型」(役立たずのレメディーを売りつける)、「公益侵害型」(感染症への効果を主張することで社会に被害を発生させる可能性がある。)
- 予防接種有害論:「財産被害型・不当表示型」(説を受け入れた個人を危険にさらす)、「公益侵害型」(感染症への効果を主張することで社会に被害を発生させる可能性がある。)
- 千島学説:「財産被害型・不当表示型」(ガン治療に効くとの主張が行われており、説を受け入れた個人を危険にさらす)
- 経皮毒:「財産被害型・不当表示型」(シャンプーを売りつけるインチキ宣伝のネタ)
- デトックス:「財産被害型・不当表示型」(健康グッズを売りつけたり施術で金を巻き上げたりするためのネタ)
- 白金ナノコロイド:「財産被害型・不当表示型」(治験が終われば治療薬としての地位を獲得するかもしれないが、十分な調査の前に健康グッズとして売るのは被害発生の可能性がある)
- 血液さらさら:「財産被害型・不当表示型」(不安を煽ることで、マイナスイオングッズを始めとするインチキ健康グッズを売りつけるための宣伝手段)
- 血液クレンジング療法:「財産被害型・不当表示型」(オゾン療法で金を巻き上げるための理屈。血液えのダメージや感染症のリスクがあり得る。)
- ゲルマニウム:「財産被害型・不当表示型」(健康グッズとして売りつけるためのインチキ宣伝文句)
- 癌克服術:「財産被害型・不当表示型」(信じた人が、治療を遅らせたりすると命の危険がある)
- ミラクルエンザイム:「財産被害型・不当表示型」(インチキ療法を広めるためのネタ)
- ゲーム脳:「公益侵害型」(第三者が広める場合は「不確かなことを言いふらす」行為になるが、提唱者がやったことは、社会の中の制度として維持している研究成果の出し方等の部分を壊すという、別の規範に触れる行為である)
- 水からの伝言:「財産被害型・不当表示型」(浄水器・活水器のインチキ評価法)
- 波動:「財産被害型・不当表示型」(健康な情報を転写する等々、インチキ商材を支える理屈)
- マイナスイオン:「財産被害型・不当表示型」(インチキ健康グッズ販売)
- 機能水:「財産被害型・不当表示型」(機能水研究財団のような、まっとうな企業努力をしている集団もあるが、これを謳うインチキもまだまだ多い)
- トルマリン:「財産被害型・不当表示型」(健康グッズとして売りつけるためのインチキ宣伝文句のネタ)
- ランドリーリング:「財産被害型・不当表示型」(効果に根拠のないグッズ)
- 燃費改善:「財産被害型・不当表示型」(買った人にとって)、「公益侵害型」(トータルで見て環境負荷増大。環境負荷を上げる行為自体が悪いわけではないが、環境にやさしいといううたい文句と逆では詐欺だろう)
- EM菌:「公益侵害型」(むしろ環境負荷を増やす)
- オーディオ:「財産被害型・不当表示型」(買った人にとって)
- 永久機関:「財産被害型・不当表示型」(投資詐欺御用達)
- 相対性理論は間違っている:
- 血液型と性格の相関:「権利侵害型」(就職差別等を引き起こしている。生物学的特徴で差別をしてはいけないというのは、科学とは関係のない規範である。)
- ID論:
- フリーエネルギー:「財産被害型・不当表示型」(投資詐欺御用達)
- スカラー波:
- 七田式右脳開発トレーニング:「財産被害型・不当表示型」(天才を生むかのような宣伝は誇大広告だろう)
- ドーマン法:「財産被害型・不当表示型」(根拠に乏しい医療行為)
- キルリアン写真:「財産被害型・不当表示型」(水評価でもインチキ評価法として登場。説明によってはオカルトとはっきりわかる場合もある)
宗教が絡む「ID論」、本を売る商売以外とは直接結びつかない「相対論は間違っている」、カルトの道具と化した「スカラー波」以外のニセ科学の多くは、商売のためのものであり「不当表示型」に分類できる。他のいくつかは、特定個人ではなく社会にも損害を与えるため「公益侵害型」の面も持っている。「血液型と性格の関係」がちょっと異質で、本人の努力で対応できない要因を理由とする社会的差別を禁じるという規範に直接違反する内容である。
「ゲーム脳」は、大学や研究者が社会に対して情報発信する時には研究としてある程度確立したものが出てくる、という、社会が前提にしている制度を壊す行為を研究者が行ったという問題がある。
これまでに出てきたニセ科学の例を見る限り、消費者被害を引き起こすという理由で既に規制や処分の対象となったものに重なる、あるいは隣接するものが相当多いことがわかる。つまり、ニセ科学のほとんどは、法が明確に含んでいる社会規範に抵触しているということである。従って、ニセ科学を問題にする、ということは、大体において、「した方が良いこと」と考えて良い。
【注】「ID論」や「相対性理論は間違っている」は、これまでのところ、ニセ科学として問題になるよりも、むしろ、従来の「疑似科学」の括りで問題とされてきた。こうして並べてみると、結果として、法規範に馴染みやすいものがニセ科学として問題となり、法規範から遠いものが疑似科学として取り上げられているように見える。
【注】差別と区別について。仮に、ヒトについての何らかの科学的測定結果がヒトの性質や能力と関係があるという結果が得られたとしても、それを社会の中でどう扱うかは、人倫における客観的真理に照らして決めることである。何らかの区別をが必要だということになったならば、その区別は、社会的差別を解消するために利用するのでなければ、社会正義にかなった結果をもたらさないだろう。なお、血液型と性格の関連については、科学としても根拠を欠いているのでそもそも前提を満たさない上に、謂われのない差別の原因を作り出すという、二重に非難に値する状況にある。
ニセ科学を問題とする行為が社会規範のあり方に影響することはあるか
ニセ科学を批判することに対して、「社会規範や道徳まで押しつけるな」と言いだす人が出てきたので検討しておく。
消費者被害に直結するニセ科学については、強制力を伴った法規制がかかっても不思議はないので、批判することが社会規範の押しつけであるといった反論には意味がない。最初から、社会規範を含んだ法によって取り締まるべき対象であり、取り締まりが行われていないというのは違法性の程度の問題であるか、運が良いかのどちらかである。
消費者被害に直結していないニセ科学については、「科学を装う」という行為を問題とすることになる。社会の中での科学の位置付けや、科学を発展させるための制度とともに確保されている信頼性を考慮すると、科学を装うという行為そのものが非難に値する。なぜなら、信頼性に乏しい内容を信頼性が高いかのように見せかける行為は、社会の側で用意した信頼性確保の制度そのものを揺るがすことになるからである。「嘘をついてはいけない」「不確かなことを言いふらしてはいけない」という規範を適用することもできるが、もう少し絞るなら、既に確立している制度を合理的な理由無しに壊してしまうからだという理由も考えられる。
なお、ニセ科学として問題になるのは科学を装っているものに限られるので、際限なく問題の対象が広がるということはない。また、非合理な言説が批判されることもあるが、ニセ科学として問題にしているわけではない。ニセ科学を問題にするということは、非合理一般を問題とするということとは一致しない。
ニセ科学を問題にした場合、今ある社会規範の存在を再確認するということは起きても、新たな社会規範を定めるとかこれまで以上に範囲を拡げて社会規範を適用するといった効果までは生じなさそうである。
違反の程度と現実に実行可能なペナルティとのバランス
ニセ科学を問題にするという行為そのものが法的裏付けを伴うわけではないから、問題にするといっても、ウェブ等で批判的にとりあげるとか、場合によってはマスコミ等を通して批判的な内容を述べるといった対応に止まることになる。違法とされた場合のペナルティとしては強制力を伴った何らかの処分が行われるところ、未だ違法とされないものについては、いろんな人からクレームをつけられる、という程度の軽いペナルティになる。
ニセ科学の中には、後日違法とされるものも含まれている場合がある。この場合は、先にニセであることを指摘することで被害発生を減らせる可能性がある。
また、法が総ての違反を引っかけているわけでもない。あるニセ科学宣伝に対して行政処分等が行われた場合、ほとんど類似の宣伝や、似ているが違法のハードルを越えるに至っていない宣伝に対して、批判するという軽いやり方で注意喚起を行うのは、規範に対する違反の程度ともバランスがとれている。
批判をされることや、批判が社会規範によって正当化されることを、ことさらに重大なことであるかのように主張する反論が出てくることがあるが、ごく軽いペナルティを重大なものに見せかけて判断を誤らせようとしているに過ぎない。
社会規範の部分を押しつけであるとすることの意味
社会規範にこれらの特定の規範が含まれていることを問題としたり、規範を押しつけるということを問題とするのなら、同時に法規範の一部も否定する立場を取っていることになる。このことを自覚すべきである。
慣習規範の性質から、ある規範が長年繰り返し守られなくなると、規範としての力は段々無くなっていくと考えるしかない。社会で規範として受け入れられていないものを法で強制するというのは無理があるから、行き着く先は、法規範まで含めてその規範が無くなるということになる。だから、本気でこれら2つの規範を将来には無くすべきだと考えているのならば、今、道徳を押しつけるなという立場で否定することはその考えと矛盾しないだろう。しかし、そこまでの覚悟がないのにうわべやその場の気分で否定だけするのは、やはり思慮不足というものだろうし、無意味に社会を混乱させると非難されても仕方がない。
また、規範が抵触するものは別の規範である。従って、ニセ科学を問題とする行為が特定の社会規範の存在を前提にしているからといって、「科学以外のことを正当化するな」などと主張することは失当である。そもそも、その「科学以外」のことは、科学者が決めたわけではなく、既に社会の側が採用している規範であり、ニセ科学の議論をする側がその存在を再確認しているに過ぎない。このような主張は、規範としての体をなしていないので、上で取り上げたいくつかの規範にぶつけて、何を正しいとするかという価値に関する考察を行うためには、全く利用できない。
批判の態度批判をする場合も、単に個人的に気に入らないというレベルの話ではなくて、きちんと基準となる規範を立てて議論しない限り意味がない。
社会における(狭い意味での)科学の位置づけ
社会における科学の位置づけとして、法規制の場合にどうなっているかをまとめておく。
景品表示法4条2項や、特定商取引法6条の2では、商品の宣伝内容について「合理的な根拠」が存在することを事業者に対して求めている。いずれの条文についても、公正取引委員会と経済産業省からそれぞれ運用ガイドラインが出ているが、内容はほとんど同じである。
商品の宣伝において「合理的な根拠」が満たすべき要件とは、
1 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
2 勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
である。
「客観的に実証されたもの」の意味は、
1 試験・調査によって得られた結果
2 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
試験・調査というのは、勝手な内容ではダメで、
(1)試験・調査によって得られた結果
1 試験・調査によって得られた結果を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合、当該試験・調査の方法は、勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施する必要がある。
<例>
・日用雑貨品の抗菌効果試験について、JIS(日本工業規格)に規定する試験方法によって実施したもの。
・自動車の燃費効率試験の実施方法について、10・15モード法によって実施したもの。
・繊維製品の防炎性能試験について、消防法に基づき指定を受けた検査機関によって実施したもの。
2 学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には、当該試験・調査は、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施する必要がある。
社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法が具体的にどのようなものかについては、勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容、商品・役務の特性、関連分野の専門家が妥当と判断するか否か等を総合的に勘案して判断する。
3 試験・調査を行った機関が商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関する勧誘・広告を行った販売業者等とは関係のない第三者(例えば、国公立の試験研究機関等の公的機関、中立的な立場で調査・研究を行う民間機関等)である場合には、一般的に、その試験・調査は、客観的なものであると考えられるが、上記1又は2の方法で実施されている限り、当該販売業者等(その関係機関を含む。)が行った試験・調査であっても、当該勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出することは可能である。
4 なお、一部の商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関する勧誘・広告には、消費者等の体験談やモニターの意見等を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠にしているとみられるものもあるが、これら消費者等の体験談やモニターの意見等の実例を収集した調査結果を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある。
とされている。
専門家の扱いは、
(2)専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
1 当該商品・役務又は勧誘に際して告げられた、若しくは広告において表示された性能、効果、利益等に関連する分野を専門として実務、研究、調査等を行う専門家、専門家団体若しくは専門機関(以下「専門家等」という。)による見解又は学術文献を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合、その見解又は学術文献は、次のいずれかであれば、客観的に実証されたものと認められる。
i. 専門家等が、専門的知見に基づいて当該商品・役務の勧誘において告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの
ii. 専門家等が、当該商品・役務とは関わりなく、勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの
2 特定の専門家等による特異な見解である場合、又は画期的な性能、効果、利益等、新しい分野であって専門家等が存在しない場合等当該商品・役務又は勧誘に際して告げられた、若しくは広告において表示された性能、効果、利益等に関連する専門分野において一般的には認められていない場合には、その専門家等の見解又は学術文献は客観的に実証されたものとは認められない。
この場合、販売業者等は前記(1)の試験・調査によって、勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等を客観的に実証する必要がある。
3 生薬の効果など、試験・調査によっては勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果等を客観的に実証することは困難であるが、古来からの言い伝え等、長期に亘る多数の人々の経験則によって性能、効果等の存在が一般的に認められているものがあるが、このような経験則を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合においても、専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要がある。
とされている。
法規制する場合には、普通に科学で行われている証明のやり方をダイレクトに求めることになっている。
問題点
- なぜ、科学の場合には、「嘘(や不確かなこと)を言い触らしてはいけない」という社会規範の権威が機能しないのか。
技術開発者さんが多用しているたとえ話で、「消防署の方から来ました」といって報知器や消火器を売りつける話がある。消防署の人が、本業のついでに「消防署は訪問販売しません」と注意喚起することは、人を騙してぼったくるのは良くない、という社会規範を前提としている。で、消火器であれば「消防署員が訪問販売しないのはわかったが、消防署員のふりをして消火器を売ってもかまわないだろう」と言う人がほとんどいない(つまり嘘をついてはいけない、という社会規範の権威が機能している)のに、話が科学になったとたん「ニセ科学が科学でないのはわかったけど、何を信じるかとか言い触らすかは個人の自由だ」という人がそれなりの数居る(嘘をついてはいけない、という社会規範の権威は機能していない)のはなぜか、という問題。普通は「それ嘘ですよ」と指摘したら、「嘘だったのか。嘘をつくのはよくないことだし、その嘘を信じて広めたりしてもよくないことだ」という反応が返ってくることを期待するのだけど。