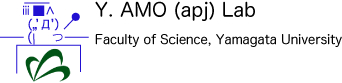「脳のなかの水分子」へのコメント(2006/09/05)
【注意】このページの内容は商品の説明ではありません。商品説明中に出てくる水の科学の話について、水・液体の研究者の立場から議論しているものです。製品説明は、議論の最後にある、販売会社のページを見てください。
| 書名 | 脳のなかの水分子 意識が創られるとき |
| 著者名 | 中田力 |
| 出版社 | 紀伊国屋書店 |
| 価格 | 1600円 |
| ISBM | 4-314-01011-8 |
ポーリングが提案した、「全身麻酔薬が水のクラスター形成を安定化させて、水分子と水分子が違いにくっつきやすい状態をつくることが、全身麻酔の作用機序である」というところにこだわって、「脳の渦理論」を考えたという話である。
ただ、この本を一冊読んだだけでは、情報が不足していて、著者が何を言いたいのかはっきりしない。鵜呑みにしたら相当おかしな話になりそうに思う。一般向けの本でも、もう少し実験事実を出してくれないと、何がどこまでわかっているのか見当がつきかねる。
48ページに「水分子のクラスター形成」の図がある。が、大峰さんの分子動力学シミュレーションに比べて、平均分子密度があきらかに小さいように見える。適当に絵を描いただけならそもそも議論の対象にもならないが、シミュレーションによるものだとすると、温度・圧力条件を明示してほしい。これまで見たシミュレーションでこの図に近いものといえば、水の超臨界状態の計算である(密度は通常の水の約3分の1)。この場合は密度揺らぎが大きくなることが知られている。
59ページのポーリングを引用した部分。
ポーリングは、キセノン麻酔から出発して、脂肪溶解度説という定説とは比べものにならないほど論理的で、説得力のある結論に到達した。キセノンを含むすべての全身麻酔効果のある薬品が水のクラスター形成を安定化さし、小さな結晶水和物を作り出すことを見つけたのである。ポーリング自身は「水和性微細クリスタル説」と呼び、私たちポーリングの後を継ぐものが「水性相理論」と呼ぶ理論である。ポーリングは水分子と水分子とがお互いにくっつきやすい状態をつくることが、全身麻酔効果の分子機序であることを発見したのである。
キセノンを水に混ぜたって、室温じゃさほど溶けない。結晶水和物が出来る温度と圧力はどれくらいなのか?人体に理論を適用したいのなら、36℃1気圧でその状態ができる実験的証拠がまずないと、どうにもならないのだが、この点について本には何も書いてない。
さらに、59ページの後半は論理が飛びまくっていて、本当に起きているのがどういう現象なのかがわからない。
全身麻酔薬は、大気圧の低いところではより大きな効果を示すのである。大気圧の低い上空を飛んでいる飛行機の中では、同じ血中濃度を示す麻酔薬の量で、さらに深い麻酔がかかるのである。
(中略)
ところが、全身麻酔薬による結晶水和物の形成は、わずかな大気圧の変化で大きく変わるのである。
(中略)
全身麻酔薬の濃度が同じでも、大気圧の低い状態では、より多くの結晶水和物がつくられ、大気圧の高いところでは、その形成が少なくなる。
気体の水に対する溶解度は、一般に圧力に依存し、圧力が高いほど気体がたくさん水に溶ける。大気圧が低いということは、キセノンのようなガスを考えると、むしろ溶解度は下がるはずである。にもかかわらず、「より多くの結晶水和物が作られ」るという状況がさっぱり想像できない。試験管の中の話だとすると、一体どういう実験をしたのか。
体内では事情が異なる、というのであれば、どうやってin vivoで結晶水和物の量の圧力依存性を直接測定したのかをまずは書いてほしい。本には、結論だけが述べられていて、何を測定した結果からこう考えるに至ったのかがまるまる抜けている。
111ページに
脳の自己形成はプリューム型の熱対流に従う
(中略)
プリューム(plume)とは羽毛のことで、プリューム型の熱対流とは、風のない空に上がっていく煙突の煙のような形の、熱運動を意味する。
実際の組織には血流がある。血流のような、熱を運ぶ流れがある状態と、熱対流がどう結びつくのかが、本を読んだだけではさっぱりわからない。熱対流を記述する方程式(モデル)から脳の形が出てくるというのなら、それはそれで組織が出来るときの簡単な数理モデルを提案したという話になるのだが……。
だいぶ前に、フラクタル図形を出す計算で、脳の樹枝状のニューロンの形を出したりするのがあった。ベローゾフ・ジャボチンスキー反応をゲルを使って行い、出てくる濃淡パターンが脳のしわのように見えるものが出てくる。これを記述する反応拡散方程式で、脳のパターンも記述できるって話が出てきたりして、簡単なモデルから現実の生物に近い形が作れるということが物理屋としては面白かったのだが、こういった話と一体どこが違うのだろうか。
121ページの図の注とその前後の記述。
地球はエントロピーの低いエネルギーである光子を獲得し、同じ量のエネルギーを、エントロピーの高い熱エネルギーとして放射することによって、地球のエントロピーを低い状態に確保することができる。これが地球上にエントロピーの低い存在である生命が生まれ、維持されている理由である。同様に、脳もエントロピーの低いエネルギーとして情報を獲得したあと、情報の記憶を保つため、つまりは脳のエントロピーを低く保つためには、同じ量のエネルギーをエントロピーの高い熱エネルギーとして放射する必要がある。地球に熱放射の効率が良い夜が必要なように、脳には睡眠が必要となる。
後半の情報の部分で言ってるエントロピーは、熱力学的エントロピーではなく、情報学的エントロピーとしか受け取れない。だとすると、この記述では、もともと関係のない情報量の物差しであるエントロピーと、熱学過程を混同してしまっていることになる。これでは、何をいいたいのかまるでわからない。最後の熱放射は無意味だろう。地球は自転しているだけで、光子の輻射も赤外線の放出も常に行っていて、脳の睡眠の話とは全く関係がない。
また、この本では、脳の「渦理論」がうまれて、その主役が水だったと書いておきながら、内容は別の本を読めという不親切なことになっている(別の本=「脳の方程式 いち・たす・いち」「脳の方程式 ぷらす・あるふぁ」)。
この本のハイライトは多分、162ページ後半からである。グリア細胞に存在するチャンネル構造について記述した部分である。
私は、アセンブリーがアクアポリンであることを確信した。同時に、グリアのマトリックスに乾いた空間が存在することにも、確証を得た。アクアポリンがつないでいる空間には、水の含有量の違いがなければいけないからである。
脳には乾いた空間がある。それは、グリアのマトリックス構造と相まって、ニューロンネットワークを保護する緩衝材を作り上げている。ラジアル繊維がプリューム型の熱対流のパターンを追いかけながら形作った脳の形態は、ラジアル繊維が消失したあとの空間を乾いた空間として保つことによって、最も効果的な冷却装置を保証し、かつ、実質的な球形を保つことによって、脳皮質全体に、熱放射による等価のノイズを与える。意識とは、実質的なエントロピー空間である大脳皮質におこる最もエントロピーの高い状態、つまりは、等価のノイズが作り出す現象である。現象論的にいえば、大脳皮質のニューロンがランダムに発火している状態である。脳が情報を受け入れる準備のできている、覚醒した状態である。
意識の理論が、ほとんどその完成型に達した瞬間であった。
乾いた空間があることが、脳の中における最も効果的な冷却装置だと読めるが……普通は濡れた空間というか、水を循環させる方が冷却の効率は良い。空気を隙間に確保するというのは、むしろ断熱する時だろう。大体、装置でも何でも、空冷で追いつかなきゃ水冷するものだ。また、ニューロンがランダムに発火している状態というのは、そりゃ何かの発作を起こしている状態ではないかと思うのだが……最近の脳科学では、覚醒した状態であるということになったのだろうか。私は脳の研究者としては全くの落ちこぼれなので、誰かわかるように説明してほしい。
筆者としては脳科学の常識を覆す研究だと主張したいらしいが、普通に読むと、通常の熱力学の常識に反してそうな記述があちこちに出てくる。まあ、この意識の理論が完成した時に、筆者の頭の中のニューロンがランダムに発火していた可能性は否定できないが。
なお、グリア細胞にアクアポリン4が見つかったという記載があった。
渦理論が書いてあるとされる学術書はNakata T.(ed), Integrated Human Brain Sciece, Elsevier, 2000だそうである。