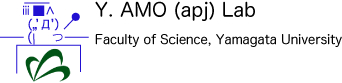経営コンサルタント(2001/12/27)
【注意】このページの内容は商品の説明ではありません。商品説明中に出てくる水の科学の話について、水・液体の研究者の立場から議論しているものです。製品説明は、議論の最後にある、販売会社のページを見てください。
出典は、孫引きだが、「経営コンサルタント 1997年2月 No.580 P.137〜142より抜粋」されたインタビュー記事で、ネットではここに掲載されている。
注意深く読むと、正しい記述もあるのだが、誤解を招きやすい表現もあるので、どこが変かについて議論したい。インタビューに答えているのは、エム・シー・エム社長 畑中賢爾氏である。インタビュアーは、多分、経営コンサルタントという雑誌の記者だと思われる。
まず、インタビューの最初に、記者が書いたと思われる、
約35億年前、地球に初めて生命か誕生した頃とほぼ同質の機能を持つ水だという。とあるが、これまでのところ、生命誕生は海の中からということになっているので、「水」が特殊なのではなくて、原始の海水の成分が大事だということになる。だから、引き続き書かれるインタビューで言われる水が、海水のことなら話ははっきりするのだが、どうもそうではなさそうな点が、読んでいて引っかかるところである。
そうです。水に特殊な圧力を加えることによって、分子運動が驚異的に活発になるんですね。そうして、究極の単分子水ともいわれる活力のある水を創り出すことに成功したんです。
圧力そのものに特殊とそうでないものがあるわけではないから、圧力の値と圧力をかける条件(時間、温度など)の条件に何か特別なノウハウがあると、まずは読んでおく。
水の温度を上げて圧力をかけると、水は超臨界という状態になる。超臨界状態は、水の相図で、液体と気体を区別する線が消えた先の状態で、液体と気体の区別が付かない状態である。シミュレーションでは、分子の数揺らぎがきわめて大きくなることが知られている。水に限らず、他の液体でも超臨界状態を作ることができる。超臨界状態の研究がなぜ行われているかというと、超臨界状態では普通では溶けない物質が液体に溶けたりするので、物質の抽出に利用したり、通常の条件では起きない化学反応が起きたりするので、環境汚染物質の融解に使われたりしている。
超臨界状態の水では、確かに分子運動が活発で、水分子間の水素結合はばらばらに切れた状態である。だから、圧力をかけると分子運動が驚異的に活発になるという話は正しいが、それを「単分子水」とは、普通は呼ばない。超臨界水と呼ぶ。
『活性化鉱水の製造方法及び装置』に関する発明として、日本をはじめ、米国なと世界八カ国で特許が認められています
とあるが、この発明に限らず、一般に、特許が認められているからといって、特許の中身で使われている科学理論が正しいとは限らない。特許は新規なアイデアを保護するものであるから、内容が厳密に正しいことを意味しない。そう思って宣伝などを読むようにしないと、宣伝を誤読することがある。このことは、「水」「クラスター」をキーワードにして、特許電子図書館を検索してみればわかる。液体の水(室温、1気圧)のクラスターを小さくすると称する装置の特許が大量に引っかかるし、17O-NMRの線幅でクラスターの評価をしたという話も出てくる。大手有名企業の特許も引っかかってきて、読むと同じ間違いを書いている。もちろん、NMRの線幅を用いたクラスター評価試験自体が、誤解に基づくものである。
汚れて弱っている水は、このクラスターが大きくなり、水の分子がいろんなものを抱きかかえて肥満化しているために、飲んでも消化管の細胞の中に浸透しにくくなっているんです。
水の吸収が能動輸送によって起こることと、飲んだ水は胃液や食物と混じってしまうことを知っていれば、この説明が変なことはすぐにわかる。人体には恒常性の維持という機能があって、水の吸収が適切に行われるようになっているから、バカ穴(半分業界用語。蛋白質のチャンネルがなく、制御してものを輸送しない単なる穴をこう呼ぶ)の開いた膜に対する浸透と能動輸送による水の吸収は直接関係しない。還元作用は、水に含まれている不純物の性質と量で決まるものであり、水自身が本来持っている性質から出てくるものではない。
この水は、水素結合が切れて小さなクラスターの状態になっていて、時間が経過してもその状態を保ちます。
(略)
一定の圧力でもって加圧し、循環させることで、水ほ臨界点に達します。こうなるともう、水は極小分子のままで元に戻らないのです。これが「水の記憶」ということなんです。
これは、完全に何かを勘違いしているとしか思えない。水が液体である以上、温度・圧力・体積が決まれば、ミクロな状態は1通りに決まる。水本来の性質として、何かを記憶することはあり得ない。もし、水分子間の水素結合が切れた状態を、室温1気圧の条件で実現したというのであれば、別の実験でそのことが確認できなければおかしい。水の超臨界状態の説明にもあるように、超臨界状態、すなわち水分子間の水素結合が切れてばらばらに水分子が運動している状態では、誘電率が79から10以下に減少する。従って、水が水素結合の切れた状態を記憶するのであれば、その水の誘電率を測定すると値が10程度になるはずである。もし、誘電率が普通の水と変わらない値であるなら、水の水素結合は通常通りに存在していると考えられる。また、水のO-H伸縮振動のピークは、ラマン散乱であれば3500cm-1付近に存在し、赤外吸収でもその付近に吸収がある。水素結合が無くなれば、分子内O-H伸縮振動の様子が変わるので、スペクトルに変化が現れるはずである。また、水の同族化合物の融点と沸点を比較すると、水だけが著しく高くなっている。もし、分子間水素結合が存在しないのであれば、その水は他の同族化合物と似た振る舞いを示すことが予想されるので、融点と沸点が数十℃下がるはずである。このような傍証が示されないうちは、水が水素結合の切れた状態を保つという主張を信じるわけにはいかない。
ただ、記事に書かれているような加圧・減圧の繰り返しで、加圧のときに超臨界状態が実現しているとするなら、実験操作によっては、水にいろんなものが溶解している可能性がある。また、溶けにくい物質をよりよく溶かしたり起きにくい反応を効率的に起こさせるプロセスを見つけている可能性もある。「記憶」と考えているものの実体が、水に溶けている不純物の組成の違いで説明できるかもしれない。それはそれで産業に利用できる話なので、水本来の性質として記憶効果を考えるよりは、どういう条件で何が溶けたかちゃんと調べた方が、将来の応用につながるのではないかと思う。
ウォーターサイエンス研究会という研究機関があるのですが、そこの測定データによりますと、興味深い結果が出ているんですよ。水道水1?に、私が開発した水を使って作ったテトラポットを沈めて、経時測定をしたところ、水分子の大きさを示す半値幅は三〇分後に一四八・〇Hz、一時間後で一五一・一Hz、五時間後には九八・六Hz、二四時間後には何と五五・ニHzにクラスターが小さくなっていることがわかったんです。
(略)
NMR(核磁気共鳴装置)です。水のクラスターというのは世界的に認められているんです。 NMRは通産省も認めている現状では究極の分析装置で、HIVの世界でもNMRで調べるんです。
NMRの半値幅で液体状態での水クラスターのサイズがわかるという話は、誤解によって広まったものである。NMRでは、直接水クラスターのサイズの情報を得ることはできない。また、上記の半値幅が17ONMRであれば、中性付近でpHの指標になることがわかっている。だから、上記の記述は、「ウォーターサイエンス研究会がNMRを正しく理解していない」ということに尽きる。
液体状態での水クラスターの話は、世界的に認められていない。いろんなデータの解析の際にモデルとして使われることはあるが、それでも書き方によっては曖昧だという理由で論文の掲載を断られるというのが現状である。ウチの研究室でも、水クラスターを持ち出して議論した論文が、あちこちでリジェクトされて結局つぶれたということがあった。
世界的に認められている水クラスターとは、例えば、水のジェットを真空中に吹き出させ、断熱膨張で分子数個から数十個でできた微小液滴である。これを分子線クラスターといい、水だけでなく、水溶液や有機溶媒でも作ることができる。作ったあとは、分光したり質量分析をしたりして性質を調べる。また、電圧をかけた針に液体を導入し、イオン化したアルゴンガスを流して、液体表面付近からクラスターを作る方法もある。分子線クラスターと同様に、質量分析などがなされている。いずれにしても、認められているクラスターとは、気相中に微小液滴を作ったものであり、巷でいわれているような液体状態での水クラスターの話とは全く別物である。
NMRそのものは、広く使われている分析方法で、確かに強力だが、究極の分析装置というわけではない。NMRで測れるものもそうでないものもある。また、NMRで水クラスターの測定ができるということを示した、まともな論文はない。通産省が認めているのは、おそらくNMRという方法が分析に便利だということまでで、水クラスターの評価手法の標準だということを認めたわけではないだろう。
「活性化」された水が他の物質に「共鳴」して、その物質をまた「活性化」するかのような記述があるが、この記述は科学的でも何でもない。「活性化」が水を分子レベルでどう変えるのかがはっきりしないし、そのことが他の物質に共鳴する条件も不明である。仮に、記事の主張に従って考えるならば、水素結合が切れた水が実現してそれが活性化状態すなわち高エネルギーで不安定状態であるというのが前提になる。そうすると、再度水素結合を作るときにその差の分だけのエネルギーを他に与えるということになるが、これは共有結合よりも1桁以上小さいエネルギーなので、化学反応に関与するとは思えない。水素結合分のエネルギーをちょうど受け取れるエネルギー準位差が、相手方の物質にあれば共鳴も可能なのだろうが・・・・結合を変えるほどのエネルギーでなければ、熱になって散逸して終わりである。(もちろん、室温1気圧で単分子水が実現するという話自体に、今のところ信憑性がないので、この段落の議論は架空の議論であるが、それでも他の物質の活性化にはつながらない)
この後に書かれている、社長が哲学を語っている部分は読み飛ばすことにして、最後の方で、またちょっと変な記述がある。記者が書いた見出しに
活性化された物質から不思議な“電磁波”が出てくる
とある。
電磁波が出てくるかどうかは、イマドキのことだから、測定装置さえきちんと扱えば確認できる話である。ただ、出てきた電磁波のエネルギー合計と、「活性化」で与えたエネルギーとはちゃんとつりあっているのでしょうね?「活性化」でどれだけのエネルギーを物質に与えうるかという評価を、どうやって行っているのか、この記事だけではわからない。非常に知りたいと思う。
—それで、そのペン先はどういう特性があるのですか。
畑中 シータ波が出ます。
—シータ波?
畑中 直観力を誘発する脳波です。そのものずはり、シータという商品名で全国のデパートで販売されています。
この記述だと、「物質から直接脳波が出る」ということになっていて、既に別世界なんですが。その製品を使った人の脳波を測定するとシータ波になる、というならまだ話はわかるのだけども。脳波は、脳の中の細胞の活導電位を頭の外からまとめて測定したものをいうから、物質から出るものを脳波とは呼ばないのではないだろうか。
—成果を学会に発表されないのですか。
畑中 東北大学のある教授も「これは新しい科学としかいいようがない」といっているのですが、発表すれはあまりにも反響が大きいでしょうからね。むしろ、実業レベルでいいものを作って売り出すというのがいいんじゃないでしょうか。それが最後は官を動かし、全体を動かすと思いますよ。
学会や学者をまったくわかっていない発言である。我々は普段、如何にして反響の大きい発表をするかということに心を砕いている(もちろん、反響の大きい優れた研究成果を出す、という意味で)。また、自分が先に発見していても、誰かに発表されて論文を出されてしまうと、発見者の名誉は発表した人のものになる。我々の世界では、1番乗りというのは非常に重要なことなのだ。反響が大きいから発表しないというのは、似非学者か官僚のすることである。
逆に、サイエンスの枠組みのチェックを受けずに動いてつぶれた話の有名なものに、常温核融合がある。常温核融合では、学会発表でも論文でも、十分な追試ができるだけの情報が出されず、その代わり特許や産業応用の話や予算獲得のためのロビー活動が先行した挙げ句、病的科学であるということで決着がついた。この騒ぎに学ぶつもりがあるなら、特許を申請した後でかまわないから、事業レベルに持っていく前に、きちんと原理の確認につながる実験結果を学会で公表し、抜けているところがないかどうかチェックするべきだと思う。水素結合の変化を検出するのであれば、NMRよりむしろ、X線や中性子線回折など、直接分子の空間分布を見る方法の方が有効だし、前述したように、光を使って測定することもできる。いろんな測定法で矛盾しない測定結果が出てくることをまず確認してからでないと、幻に基づいて製品開発や商売をするという不健全な方向に進みかねないと思う。「新しい科学」が本物として認められるためには、誰もを納得させるだけの明白な証拠が必要なのだ。