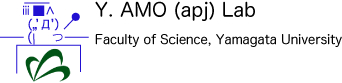「電気石が作る水の界面活性」へのコメント(2002/08/12)
【注意】このページの内容は商品の説明ではありません。商品説明中に出てくる水の科学の話について、水・液体の研究者の立場から議論しているものです。製品説明は、議論の最後にある、販売会社のページを見てください。
元の報文は、「電気石が作る水の界面活性」、久保哲次郎、固体物理 vol.24, No.12 (1989) 1055-で、ここで全文を読むことができる。
まず、久保氏は、電気石(トルマリン)が、自発電気分極を持つことを紹介し、磁極に対応して「電極」と呼ぶことを提案している。トルマリンは確かに磁石に対して「電石」と呼べる物質だから、この呼び方自体は(まだ認知されていないにせよ)不都合はない。自発分極を持つ物質のことを焦電体と呼ぶ。焦電体のうち,自発分極と逆向きの電場をかけたときに分極が反転するものを強誘電体という。焦電体は絶縁体である。
実験(1)では、電気石の含まれた砕石を、硫酸銅水溶液に浸して観察を行っている。結果は、まず溶液中の銅イオンの色が消失し、3日おくと、鉱石の電気石の含まれた部分に緑青ができて色が緑色に変化した。同じ電気石の露出している部分でも、この変化がないところもあった。これから、銅が電気石表面に電着されたこと、電着の有無の差は電気石のアノードとカソードに対応するという結論を導いた。
どうやら久保氏は、電気化学で出てくる、電解漕のアノードとカソードを連想したらしい。しかし、この実験で起きた現象の説明としては適切とは思えない。実験(1)で起きたのと同じ現象は、高校の化学のイオン化傾向の話で出てくる。イオン化傾向の小さい金属イオン(Cu)が溶けている水に、イオン化傾向の大きな金属(Na, K, Ca, Mg Al など)を入れると、イオン化傾向の小さい金属が電子を溶出してイオンとなり水中に溶けだし、銅は電子を受け取って金属表面に析出する、というものである。そのまま放置しておけば、析出した銅で緑青ができる。鉱石を試験しているわけだから、金属成分の溶出のしやすさに違いがあれば、銅が析出する部分とそうでない部分が出てくるのは当たり前である。電気石のアノードとカソードに対応するという結論は、この実験から直ちに出てこない。どうしてもそういう結論を導きたければ、鉱石ではなく、ある程度の大きさで結晶の方向が決まった電気石を用いて同様の実験を行い、金属成分の溶出のしやすさが結晶面によってどの程度異なるのかも同時に評価する必要がある。もちろん、この現象は、電気化学でいうところのアノードやカソードとは何の関係もないし、電気分解とも無関係である。
実験(2)では、電気石の自発分極の消失する温度を調べるために、同じ砕石を950℃から1050℃に1時間加熱した後に、実験(1)と同様の実験を行い、900℃、950℃では実験(1)の結果を再現したが1000℃、1050℃では再現しないという結果を得た。このことから、永久電極の消失する温度は950℃から1050℃であると見積もった。さらに、実験(1)を、銅だけでなく、銀、ニッケルの電着も行った。そして、永久電極の存在と、高温での加熱によって永久電極が消失するという結論を導いた。
久保氏自身が最初に書いているように、電気石の自発分極(久保氏のいうところの永久電極)は、その組成と結晶構造によるものである。従って、加熱をしたことによって結晶構造が変われば、当然自発分極は無くなる。また、結晶構造が変われば成分の溶出の仕方が変わることも考えられる。自発分極の消失確認したいのであれば、素直に分極の大きさを測定すれば良いし、その理由を知りたいのであれば、X線などを使って加熱の前後で結晶構造が変わったかどうかを調べれば済むことである。水に入れるというのは、実験方法としてそもそも適切でない。さらに、「電着」を調べているが、用いている金属は銀やニッケルといった、トルマリンに含まれる金属成分よりもイオン化傾向の小さいものを用いているから、同じ結果になるのは当たり前ではないだろうか。
久保氏は、本文中で「電気石が永久電極を持つ珍しい存在であるにもかかわらず、今日まで宝石以外の利用について研究されなかったことの方がむしろ不思議である。」と書いている(1056ページ右側)。こういうことは、きちんと文献検索をしてから言うべきだ。この報文が書かれたのは1989年だが、それ以前にも、圧電素子としての利用研究はちゃんと行われている。
§3では、電気石の応用の可能性として、電気石を砕いて数ミクロンにしたものと、セラミックの粉を混ぜて焼き固めたものを作って通水装置を作ったことが述べられている。電気石の反対符合の電極がお互い電極がうち消しあわないように、電気絶縁性の高いセラミックで間を埋めたと書かれている。シリカやアルミナによって埋められた電気石は、電極(=自発分極)を失う温度が100℃から200℃高くなった。
電気石の分極は、結晶軸の向きに依存する。電気石を粉にすると、それぞれの粒の結晶軸はデタラメな方向を向くから、全体として分極は打ち消し合ってしまうだろう。この状態で電気石の粉末の間に絶縁体を置いても意味がない。電気石自体、そもそも絶縁体である。電気石の分極の効果を確認したいのであれば、結晶軸のわかっている単結晶を使うべきである。
§4の、水の電気分解の記述は部分的には正しい。しかし、1057ページ右下のところに、
水の中に電気石の電極がある場合、H+イオンとOH-イオンは各々のイオンの反対符合の電極面に向かって移動し、電極の間には電流が流れることになる。
と書かれているが、これはとんでもない誤解である。確かに電気石は自発電気分極を持つから、結晶表面に正負の電荷が現れる。要するに常に静電気を持っているような状態である。静電気があるとホコリがくっつくのは日常よく経験するところで、電気石表面も、そっとしておけば空気中に漂っているホコリなどがくっついて、電荷を中和してしまい、見かけ上電荷が出なくなっている。この状態で圧力を変えたり温度を変えたりすると分極の大きさが変化し、その変化分だけの電荷が表面にあらわれる。
電気石を水に入れた場合、表面がきれいであれば電荷が出ているから、水分子やイオンがそれぞれ反対の電荷をもった表面に引きつけられるということは起こる。水分子は酸素側が−、水素側がプラスの電荷を持つから、水分子が電気石表面で配向するということもあるだろう。だがそれだけである。電流が流れるといっても、分子やイオンが再配置されるときに一瞬だけ水の中の電荷分布が変わったことによる分だけであり、その後は電流が流れ続けることはない。
なぜなら、電気石は自発電気分極を持つ絶縁体で、自由電子を持たないからだ。電気石の中を電流が流れることはない。うんと高い電圧をかけると絶縁破壊という現象が起きて流れることもあるが、これは雷と同じである。一方、水の電気分解をするときには、金属などの電流が流れる物質を電極材料に使う。純水はむしろ絶縁体であり、水の中の電荷移動を担っているのは不純物として混じっているイオンである。だから、水を電気分解する実験では、電流を流しやすくするために、水酸化ナトリウムなどのイオンのもとになる物質を加える。水の中ではイオンは拡散することで電極表面に移動し、電子のやりとりは電極表面で起きる。電子のやりとりによって生じた電荷の偏りは、電子が金属内部を流れることで解消されるため、電流として観測できる。水を電気分解するには、電極材料内部を電子が通過できないとだめである。電気石は絶縁体で電気を通さないから、水の電気分解にはそもそも使えない。
1058ページの記述も、電気化学を知らないとしか思えないものである。
この電圧がいわゆる水の電解電圧以下である場合は第3図のDより左の部分に当たり、カソード面での水素ガスの発生はあってもアノード面においては酸素ガス発生は生じない。粒状物表面の微小な電気石電極間の電圧を測定することはできないが、実験的には水の電解電圧以下のものであることを示している。仮に電解電圧以上であるならば、電気石電極は腐食されてその腐食が進行して実用上使用できない。
電解電圧以下だと、どうして水素が発生するのに酸素が発生しないのか、まったくわけがわからない説明である。電気分解のプロセスで水素が発生するということは、水素イオン(H3O+)が1電子還元を受けているということを意味するから、しっかり電気分解が起こっていることになる。反対側では当然酸素が出るはずである。観察した結果がそうでないのなら、起きている現象を「水の電気分解」であると考える事自体が間違っている。
電解電圧以上だと電気石電極が腐食するというのも意味不明である。電気分解を行う際に、白金や炭素棒を電極に用いた場合は、電解電圧以上をかけても電極が腐食することはない。イオン化傾向の大きい鉄や亜鉛を電極に用いて電気分解を行うと、電極が溶けることがある。しかし、電気石は絶縁体だから、金属のような腐食は起きない。電気石自身が電気分解とは無関係にわずかに溶解することは起きるかも知れないが、いずれにしても電気分解とは無関係である。
その次の、水素結合を介したプロトン拡散のメカニズムの記述は正しいが、その後の記述がまた意味不明である。
このようにOH-イオンの移動速度がH+イオンの移動速度に比べて1/2近くも遅いという理由と、H+イオンは電極面で比較的容易に放電、析出してH2になり、ガスとして水から失われる一方、水の電解電圧以下ではOH-イオンは電極面での放電電位が大きく、そのまま吸着または水の中に拡散されるという二つの理由によって、OH-イオンはH+イオンから遊離して水の中でリッチな状態になる。このOH-イオンのおかれた状態はエネルギーの上からも不安定であり、活性化した状態にある。
対イオンもないのにOH-イオンだけが勝手に水の中で増えていくという主張だろうか。水のイオン積は各温度に対して決まっており、勝手にOH-だけが増えるようなことはない。必ずOH-の対イオンが存在するはずである。第一、OH-イオンとH+イオンの拡散速度の違いでH+の方がたくさん発生するというのであれば、通常の電気分解でも同じ現象が観測されなければおかしいが、そんな報告はない。
界面活性の説明も間違っている。親水基と疎水基の両方を持つ、という一般論は合ってるのに、
ヒドロキシル・イオンの構成は単純で、水の分子H2OとOH-の結合したものである。親水基の部分に相当するのはH-O-Hの部分であり、残りのH-Oの部分、特にH-の部分が疎水基の役目をする。
と書いている。ヒドロキシル・イオンはそのままの形で水分子の水素結合ネットワークにはまって運動している。両側で水素結合を作るものは、どっち側から見ても親水性である。上記の記述は、親水基と疎水基について基本的な理解が欠けているとしか思えない説明である。
対称のイオンであるHイオンを失ったこのヒドロキシル・イオンは、エネルギー的に不安定な状態でえあり、界面活性エネルギーなどを消費しようとする活性化状態になっていると考えられる。このモデルの妥当性については、今後検討を加えてゆかなければならないと考えている。
この水の界面活性作用、特に乳化作用について述べる。
この後、重油を水に分散させたエマルジョンについて、乳化作用の指標となるHLB値についての実験結果が述べられている。
ここまでの議論で、問題のOH-イオンの濃度については何も出てこない。OH-が単独で増えるという、化学の教科書の内容を丸ごと無視した話であることが最大の問題ではあるが、それでもそう主張するのであれば、せめて、まずはOH-の濃度の定量をするべきではないだろうか。また、エネルギー的に不安定であれば、もっと基本的な測定法(分光実験や、もっと単純な化学反応)でも違いが出てくるはずである。HLB値の評価は、少なくとも、「OH-が対イオンなしで存在してエネルギー的に不安定な活性化状態」が実現しているかどうかを直接確認できる実験ではない。応用を考える前に、そういう状態が実現しているかどうかを、もっときちんと確認すべきではないか。
まあ、モデルであると主張して、これからの検討の余地があると書いてはある。しかし、科学者がモデルを立てる場合、通常は、従来わかっていることの範囲でまずは考えてみるものだ。詳細に実験して、どうしても従来の知識では説明できないことがわかってはじめて、別のモデルを作ることになる。久保氏が提案したモデルは、化学の教科書の記述を大幅に変えるものであるから、本気で主張するのであれば、HLB値の評価どころではないもっと決定的な実験的証拠が必要である。ただ、ここまでの記述を読んだ限りでは、通常化学で行われる手順も無視されているように見える。モデルを検討するのなら、化学の基礎を勉強しなおしてからにすべきだろう。
§6の、実用化について、ではこう書かれている。
電気石粒状物の流動層を通った水が化学薬剤を全く用いずに界面活性を示すことは非常に大きな実用上の可能性を提起している。また、この界面活性作用の他にも次のような作用がある。
(1)酸性、アルカリ性を問わず水のpH値を中性に向かって移動させる。
(2)水の溶存酸素を増加させる。
(3)水に溶解している溶存塩素の加水分解を促進して、Cl2をHOCl、OCl-などに変え、塩素の刺激、味、臭いを著しく緩和する。
(4)弱い酸化、還元作用を示す。
(5)凝集効果などを示す活性シリカなどのポリマーをつくる。これは粒状物を構成するアルミナ、シリカ、酸化鉄などのイオン化電極反応によるポリマー架橋作用によると考えられる。
これだけのことを主張しておきながら、電気石粒状物の流動層を通過した水の成分の変化については、久保氏は何も述べていない。上記に示された変化は、明らかに化学的変化であって、水の物理的変化ではない。水の性質は、温度と圧力が決まれば一通りに決まるものであり、それ以外の変化があるとしたら、水に溶けている物質によるものと考えるべきだ。だから、「化学薬剤を全く用いずに界面活性を示す」などと言う前に、水に溶解している成分の変化をしっかり定量するべきなのだ。水は、微量であれば何でも溶かす液体であり、容易に不純物が混入する。特に、表面積の大きな電気石粒状物を通過させたりしたら、何がどれだけ溶出して混じるかわかったものではない。
久保氏が行った実験とそれに基づく主張は、水の電気分解を考えるのではなく、電気石から成分の一部が溶出したと考えても十分説明できるし、その方がずっと妥当だろう。水素の発生は金属成分の溶出で説明できる。銅が表面に析出したことも、高校化学で出てくる金属のイオン化傾向の違いで説明できるだろう。「電極」の正負の効果を考えるよりは、結晶の溶解のしやすさが結晶面によって異なると考えた方が、よほど従来の物理や化学の枠内での説明ということになる。高温で「電極」が消えたときには、その効果で結晶構造自体が変化したはずだから、水に対する成分溶解のしかたが変わっても不思議はない。界面活性や乳化作用は、水に塩基性の不純物が混じったためだと考えても説明できるのではないか。
久保氏は、どうやら、静電現象と電池などの電源とを混同するという初歩的な間違いを犯したらしい。さらに、電気石の電荷が出ている部分を「電極」と名付けた挙げ句、電気分解などで使う「電極」と混同してしまっている。日本語だとたまたま同じ「電極」と書くが、英語に直すと、電気石の電極は磁極にならってelectric poleとでも呼ぶことになり、電気分解のときのアノードやカソードはelectrodeと呼ぶ。まったくの別物である。
「固体物理」という雑誌は、けっこうまともなレビューが掲載される雑誌であるのに、こんな誤りを堂々と載せていたことを知って、私は正直いって非常に驚いている。難しいことを間違えたのなら仕方がないとも思うが、高校の化学と電気化学の初歩を知っていれば回避できる誤りである。
もし、学生が、この「電気石が作る水の界面活性」のような内容のレポートや論文を提出してきたら、間違いなく再提出だろう。ことによると、補習が必要かもしれない。基本的な化学の知識が欠落している報告など、そのまま認めるわけにはいかないからだ。
科学の世界では、何か現象を観測したときには、これまでにわかっている科学の枠組みで説明できないかをまず考える。どうしてもこれまでの枠組みで説明できなければ、新しい枠組みを考えることになり、この繰り返しで科学は進歩していく。ただし、このときには、誰もを納得させるだけの実験的証拠が必要になる。電気石を使って起きたことを説明するために、まず最初にしなければならないことは、電気石から何がどれだけ溶け出したか定量するということだ。その次に、水の性質の変化が成分の変化で起きたかどうかを確認することになる。これは、電気化学の成果と静電現象の記述の両方を無視して電気石で電気分解ができるという説に飛びつく前に、当然やっておかなければならないことである。久保氏のレビュー(おそらく研究の流れそのもの)は、この手順を踏んでいないという欠陥がある。
謝辞には、中村輝太郎教授への感謝が述べられている。トルマリンの文献検索結果を見ると、11番と17番の文献で、故中村輝太郎教授と久保氏が共著者として並んでいる。故中村輝太郎教授は、冨永教授との共著の論文(冨永教授の業績リストの5番から11番あたりに並んでいる。そもそも冨永教授の元上司だったりするし、「強誘電体と構造層転移」という本も一緒に書いている。)もある、固体誘電体の研究者で一時期の固体誘電体研究の進歩を担った人で、科学研究の手順を把握したプロのはずだ。中村教授がついていながら、なぜ、成分の分析をしろという適切な助言がなされなかったのだろうか。電気石で水を電気分解するなどというアイデアは、固体誘電体の研究としても水の研究としても、まともなものとは思われない。研究のプロが一体何をやっていたのかと小一時間問いつめたいが、残念ながら中村教授は既に墓の下である。
この固体物理のレビューだが、本気で信じ込んで活水器を作っている会社を実際に目撃した。大阪の展示会で見かけたが、製品の横に堂々コピーが置いてあった。製品に科学的根拠があると主張したいらしい。こういう会社は他にもあるだろう。挙げ句に、トルマリンを水に入れると永久に微弱電流が流れるなどという、いつからトルマリンが永久機関になったんだと突っ込みたい説明も出回っている。故中村教授がトルマリンで水の質を変える仕事を始めたころに、ちょうど冨永教授も水のダイナミクスの研究を開始していたので、いろいろ訊かれたらしい。「一体何を教えたのか?元部下としての責任はどうなってるんだ」と冨永教授を問いつめたところ、「普通の水の話しかしてないし、変なことは教えてない。またその仕事は上司でなくなってからのものだから元部下の責任はない」と言われてしまった。冨永教授の弟子の私のところには、トルマリンの効果(電気分解、永久電流など)は本当かという問いあわせが後を絶たない。師匠の上司が蒔いた種を刈るハメになっている気もするが、とりあえず遠慮無く刈り取らせていただく。
【補足】(2002/08/21)
上記の議論の中で、「トルマリンからの金属成分の溶出」を仮定したが、これが実は疑わしい。最近測定した人によると、トルマリンを水に入れても水素が発生しなかったという結果とのことだ。トルマリン鉱石には、成分や成立条件にばらつきがあるから、常に全く同じ結果になるかというと、その保証はないと思われる。もし、本当に水素が発生したのであれば、「金属成分の溶出」で現象を説明できるが、水素が出なかった場合は、また別の説明になる。
もし、トルマリン中で、ナトリウム等は酸化物で存在しているのであれば、ナトリウムやカリウムが溶液中に溶出しも価数に変化はなく、銅イオンの金属銅への還元も起こらない。この場合は、イオン化傾向で説明するよりも、ナトリウム等が溶出したことでpHが上昇し、銅が水酸化物等で沈澱したと考えることができる。ケイ酸ナトリウムからのナトリウムの溶出が起きている可能性がある。
こうなってくると、水素発生については、実際にいろんたトルマリンで試してみないとはっきりしたことがいえなくなってくる。それでも、水素が発生してもしなくても、トルマリンが電気分解に寄与しているという以外の(従来の化学による)説明は可能である。